Непомітний бичачий ринок криптовалют
«Бичачий ринок уже тут, але чому в чатах так тихо?» — з таким питанням до спільноти Opensky звернувся учасник під ніком Tongxin Cheese.
«Бо більшість уже або вийшла з ринку, або відкрила шорти», — відповів Найнор, ще один учасник.
Найнор, який пережив не одну фазу зростання і спаду, вважав цей бичачий цикл справжньою нагодою для великих заробітків. Однак сам він відверто визнає: «У цьому циклі я нічого не заробив».
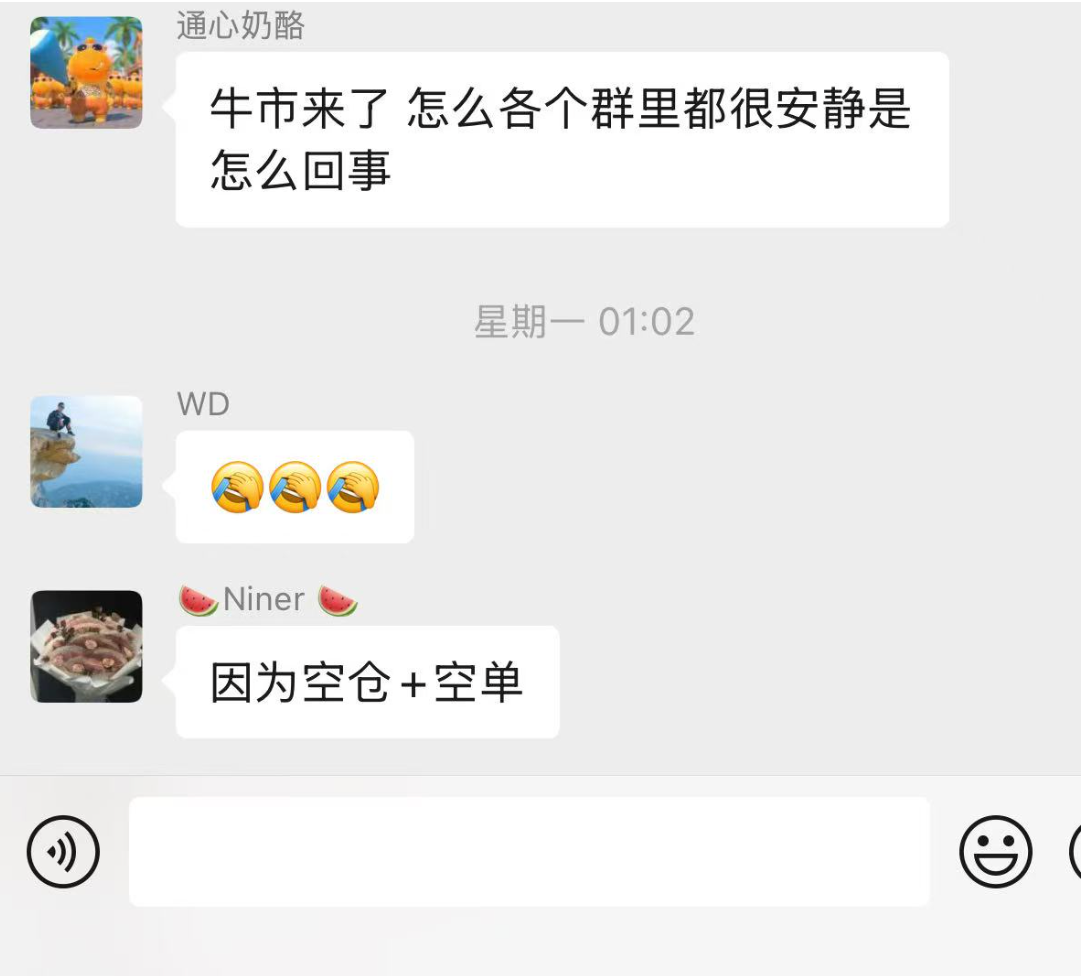
Джонні, професійний трейдер у схожій ситуації, підсумовує: «Я не отримав прибутку з моменту запуску Trump».
Найнор і Джонні — типові представники ринку. Як зазначає партнер Wagmi Capital Марк: «У нинішньому бичачому циклі 90% роздрібних інвесторів залишаються без прибутку».
Найнор поки не зміг досягти прибутку, але вже переглянув свою стратегію: «Минулого разу я просто тримав активи до останнього. Тепер зосереджуюся на свінг-трейдингу. З’явилася маса нових трендів, і треба постійно вчитися — усе рухається значно швидше».
Зміни Найнора виявилися своєчасними, але більшість інвесторів не встигають адаптуватися до ринку.
«Інвестиційна логіка цього циклу кардинально змінилася, а роздрібні учасники ще не встигли перебудуватися», — зазначає KOL Hippo в інтерв’ю.
Із приходом великих грошей у крипту та систематичним оновленням історичних максимумів лідерами, ринок перестав бути ареною для роздрібних. Змінилися всі аспекти: ліквідність, рухи капіталу, технологічне впровадження й наративи. Дедалі більше експертів вважають, що період роздрібних прибутків добігає кінця і цей бичачий цикл може стати останнім значущим для приватних учасників.
Враховуючи це, TechFlow опитав гравців різних рівнів — впливових лідерів думок, партнерів приватних фондів, алгоритмічних трейдерів та представників роздробу — аби комплексно проаналізувати поточний бичачий цикл і ситуацію на ринку криптовалют.
Нова епоха бичачого ринку в крипто
Хіппо, який працює з криптовалютою з 2016 року, добре розуміє її механізми. В інтерв’ю він стверджує: «Тепер ринок функціонує не так, як раніше. Колись у бичачі цикли все зростало завдяки єдиному консенсусу — нині політика, капітал і нові альянси формують зовсім іншу траєкторію».
Маючи досвід у військовій сфері та інвестиціях у комерційну нерухомість, Хіппо виробив підхід, що поєднує сміливість і обережність. Пройшовши кілька циклів, каже: «Я завжди думаю, що справді має довгострокову цінність у цій індустрії й які активи переживуть і бичачі, і ведмежі ринки».
Попередні ринкові цикли були невизначеними, але цей допоміг Хіппо знайти відповіді.
«Добре подумавши, я зрозумів: ця індустрія — це фінансовий інтернет. Кредитування, торгівля, стейкінг, а також нові тренди на кшталт токенізованих американських акцій і стейблкоїнів — це все фінанси. Для них потрібна сильна фінансова інфраструктура», — говорить Хіппо. — «З огляду на це, я бачу значний потенціал в Ethereum, тому фокусуюсь саме на ньому і DeFi-активах».
На думку Хіппо, цей бичачий ринок стартував із затвердження Bitcoin ETF компанії BlackRock. Після короткої корекції друга хвиля почалася з ухвалення “Great Beauty Act” у США, а пік він прогнозує на листопад.
Марк натомість має інший погляд.
Він вважає, що початок поточного циклу припав на торішній стрибок мемкоїнів — це була перша частина, а зростання Ethereum запустило другу фазу. Пік він очікує у вересні.
«У 2017 році був суперцикл ICO, потім бум альткоїнів. Але зараз усе інакше: ніхто більше не купує гучні ідеї — більшість концепцій спростовано, залишились лише фінансові застосування. Навіть після зростання Ethereum історичний максимум не оновлено, а майже всі альткоїни дають прибуток лише на окремих сегментах», — переконаний Марк.
Ще один досвідчений гравець ринку — Ченхуа, керуючий власною алгоритмічною арбітражною стратегією.
На ранньому етапі цього циклу Ченхуа зауважив: якщо раніше ринок рухали роздрібні інвестори й стрімкі стрибки малокапіталізованих монет, то тепер основним мотиватором став великий інституційний капітал, який масово спрямовується у біткоїн.
Попри чималий досвід, навіть Ченхуа втратив позиції: він ще зберігає трохи біткоїнів, але основний портфель продав на прориві $100 000, а також вийшов з Ethereum на мінімальних значеннях і не скористався відновленням. Навіть експертам дедалі складніше вгадувати моменти для входу й виходу — і для роздрібних учасників це ще важче.
Які можливості залишилися для роздробу?
Професійний трейдер Джонні зазначає: «Головна риса цього бичачого ринку — надто багато токенів, замало інновацій, ліквідність слабка, і роздрібним заробляти дедалі важче».
У попередньому циклі Джонні зайшов у ринок, коли Dogecoin розкручував Ілон Маск, і зумів отримати значний прибуток на загальному стрімкому зростанні. «Я навіть не розумів, як читати свічкові графіки, але мені вдалося заробити», — згадує трейдер.
Але ті часи залишились у минулому.
«Схеми минулого циклу зараз не працюють», — пояснює Джонні. — «Тоді досить було просто тримати активи чи йти за натовпом; нині треба створити власну торгову систему».
При цьому «на “сміттєвих” альткоїнах такий потенціал зростання зник. Фінансовий поріг і технологічна планка істотно зросли, а вигідні ідеї знайти набагато складніше».
Чому зараз роздрібним настільки важко отримати прибуток у бичачій фазі? Які дійсні можливості?
Марк називає дві ключові причини труднощів роздробу:
По-перше, більшість ще “живе” минулим циклом — переважно тримають альткоїни, а не лідерів ринку.
По-друге, постійна зміна позицій. «Погоня за пампами і панічні розпродажі — типові провали роздрібних, головний ворог прибутку», — переконаний Марк.
Він вважає, що найвигідніші можливості цього циклу — у блакитних фішках і мемкоїнах. Але зі зростанням ліквідності з’являється новий тренд: «Нові токени на Binance зазвичай зростають у 2–3 рази, а раніше ціна часто обвалювалася. Тому більшу частину капіталу я тримаю в Ethereum, а невеличку частину спрямовую в нові лістинги з розрахованим ризиком».
«Та реально можливостей для роздробу стає все менше». Марк налаштований скептично: крипто усе більше нагадуватиме ринок акцій США, де “сині фішки” належатимуть установам. Для роздрібних залишаться лише мемкоїни, але тут треба бути дотепним, наполегливим, витрачати час — саме тому прибуток отримає лише кожен десятий трейдер.
Хіппо погоджується з Марком частково, але радить спостерігати за токенами, пов’язаними з ринковою інфраструктурою.
Такі активи мають ключове значення, їх не оминути; якщо вистоять — привернуть потужний консенсус і потенціал зростання.
«Перше, що потрібно змінити роздрібному інвестору, — мислення. Треба забути про швидке збагачення», — наполягає Хіппо. — «Ймовірно, 30-кратних чи 100-кратних доходів на альткоїнах вже не буде, але на “синіх фішках” можна заробити у 3–5 разів за цикл. І завжди в бичачих циклах трапляються проривні мемкоїни. Якщо опинитися в правильній хвилі, можна отримати гарний результат».
Більшість простих і низькоризикових стратегій минулих років — як торгівля новими токенами і мінт інскрипцій — практично зникли.
«Або спробуйте мій шлях — алгоритмічний трейдинг. Він потребує навчання, зате ризик менший», — рекомендує Ченхуа. — «Я вважаю, що біткоїн досі дає кожному справедливий шанс. Якщо протриматися і використовувати стратегію середньої вартості, рано чи пізно отримаєте віддачу».
Чи завершилася золота епоха роздрібної крипти?
Ще на фіналі минулого циклу багато хто казав, що золота пора роздрібної крипти завершується через прихід інституційних гравців.
Роздріб залишається учасником ринку й нині, але інституціоналізація суттєво прискорилася.
На липень 2025 року активи у Bitcoin spot ETF становили $137,4 млрд, понад 400 основних інституцій, включно з пенсійними та суверенними фондами, вклалися у ETF BlackRock.
Публічні компанії тримають 944 000 BTC — це близько 4,8% запропонованого обсягу, а чисті квартальні придбання складають 131 000 BTC.
Coinbase і Binance відмічають бум продуктів ліквідного стейкінгу ETH (LSD), оскільки інституції перепаковують прибутковість ETH як інструменти з фіксованим доходом.
Ці дані демонструють: ринок криптовалют більше не належить роздрібним.
В окремих медіа назвали ціну біткоїна у $120 000 «капітальною учтою без роздрібних». У цей день «замість сенсаційних багатіїв BlackRock просто подавав 13 ETF-заявок щосекунди».
Марк таке й прогнозував: «Золота епоха роздрібних закінчилася. Восени минулого року вже було зрозуміло: це останнє вікно», — згадує він.
Він уже зафіксував частину прибутку й перейшов в A-shares.
«Але йти з ринку не збираюся. Вірю, що сектор мемів завжди дає новий шанс», — підкреслює Марк.
Найнор, навпаки, оптимістична: вона планує залишитись, адже впевнена — «найкращі великі шанси повертаються роздрібним».
«Кожен цикл уже роками оголошують останнім. Справжній “дикий” ріст — у минулому, а тепер час реальних можливостей», — упевнена Найнор. — «Я не залишаю ринок — хочу залишатися альфа-гравцем».
Хіппо дотримується такої ж думки, вважаючи, що більша структурованість і регулювання зменшать ризики й підвищать дохідність для роздрібних.
«З інституційними грошима тримати “сині фішки” вигідно. А ще ринок став прозоріший і менш ризикований», — упевнений Хіппо. — «У періоди спаду біткоїн міг втрачати 50–70%, але в бичачі фази зростає в рази. Якщо грамотно входити й управляти очікуваннями, основні монети, такі як біткоїн, — найзручніший шлях до роздрібних прибутків».
Після дев’яти років на ринку Хіппо порівнює себе з «рибою у воді»: «Я почуваюся на ринку вільно і ніколи не думав піти. Вірю: можливості для роздрібних були й будуть завжди».
Можливо, незалежно від настроїв, якщо ти поринув у ринок — піти складно. Найголовніше — не сам факт шансу, а ваша цікавість до навчання, уміння бачити тренди й дисципліна у використанні можливостей.
Відмова від відповідальності:
- Ця стаття є републікацією [TechFlow], авторські права належать автору [Ada]. З питань щодо повторного використання звертайтесь до команди Gate Learn — ми оперативно розглянемо ваш запит згідно з процедурою.
- Застереження: думки та висновки, викладені у цьому матеріалі, належать лише автору і не є інвестиційною порадою.
- Інші мовні версії статті перекладені командою Gate Learn. Не копіюйте, не поширюйте і не використовуйте ці переклади без посилання на Gate.
Пов’язані статті

Що таке Coti? Все, що вам потрібно знати про COTI

Що таке Стейблкойн?

Все, що вам потрібно знати про Blockchain

Що таке Gate Pay?

Що таке BNB?
